この連載は、アンサンブル愛好家である筆者が、アンサンブルコンテスト(アンコン)におすすめの曲を紹介していく連載です。
近年の全国大会では木管アンサンブルの中でも八重奏の演奏が多く見られるため、今回は木管八重奏におけるアンコン向けのおすすめ楽曲をまとめてご紹介します。
「目指せ金賞」の名の通り、王道から挑戦的な楽曲まで、人気の木管アンサンブル作品にフォーカスしました。難易度や演奏のポイントもあわせて記載していますので、ぜひ選曲の参考にしてみてください!
土蜘蛛伝説~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲(中~上級者向け)

楽曲情報
- 作曲者:松下倫士 (Tomohito Matsushita)
- 演奏時間:5分00秒(約)
- 編成:木管八重奏(Fl.1(Picc.)、Fl.2、Cl.1-2、B.Cl(or Cb.Cl.)、A.Sax(S.Sax)、T.Sax、B.Sax)
曲について
この作品は、能「土蜘蛛」の題材をもとに作曲された木管八重奏のための作品で、全国大会での演奏歴もある人気曲です。
全体はストーリー性を感じさせる展開で構成されていますが、音楽的にみるとテンポや拍子の変化に富んだ構成となっており、演奏者の高度なアンサンブル能力が求められます。特に変拍子による場面転換やリズムの揺れはこの作品の大きな特徴であり、拍感を共有しながら流れを止めないことが完成度を高める重要なポイントです。
中低音パートは全体の響きを支える要であり、反応の早いアタックと安定したリズムを意識することで全体の推進力を支えます。高音パートは色彩感を活かして旋律を際立たせ、全体として立体的なサウンドを形成することが求められます。
また、各パートに連符や細かいフレーズが多いため、音の粒立ちを揃えることとスケール練習による基礎力強化が不可欠です。
細部までの合わせと音色の作り込み次第で音楽の迫力や緊張感が大きく変化する作品であり、聴衆を引き込む力のある重厚なサウンドが魅力です。グレード的には上級向けに見えますが、しっかり譜読みをすればコツをつかみやすい部分も多い曲です。中高生でも臆せず挑戦してほしい曲です。
ゆきのはなびら(上級者向け)
※こちらの楽譜は店頭でのお取り寄せになります
楽曲情報
- 作曲者:福田洋介 (Yosuke Fukuda)
- 演奏時間:5分20秒(約)
- 編成:木管八重奏(Fl.1-2、Cl.1-2、Bsn.、A.Sax、T.Sax、B.Sax)
曲について
この作品は、2012年度全日本吹奏楽コンクール課題曲I「さくらのうた」でも知られる福田洋介氏によって作曲された木管八重奏曲です。全国大会での演奏歴もあり、透明感のある響きと緻密なアンサンブル構成が特徴です。雪のさまざまな表情を音楽的に描写しており、雪片のように細かい音型が全編にわたって散りばめられています。
演奏上は、テンポや調号、アーティキュレーションの頻繁な変化に加え、複雑な連符や細かいスラーの使い分けにも注意が必要で、常に拍感と音価を意識した演奏が求められます。また、シャープやフラットが多い調性で書かれているため、スケール練習によって調に合った運指を身につけておくことが重要です。ファゴットが編成に含まれているのも特徴で、中低音セクションが全体の響きに深みを加え、フルートやクラリネットの高音部と対比を成しています。一方で高音群と低音群で同一のフレーズを同じ強さ・ニュアンスで演奏すると響きが重くなりやすいため、それぞれの楽器特性に応じた音量や発音位置の工夫が求められます。
制限時間ギリギリの演奏になりやすいため、どうしても時間内に収まりきらない場合はカットも検討してみてください。
近年のアンサンブルコンテストでは、派手でスピード感のある曲が選ばれる傾向もありますが、この作品は繊細な音楽づくりを通して表現力を引き出すタイプの作品です。静けさの中に息づく情感や響きの美しさを大切にしながら、上級者が集うチームでぜ挑戦してみてください。
鬼姫 -ある美しき幻影-(中級者向け)
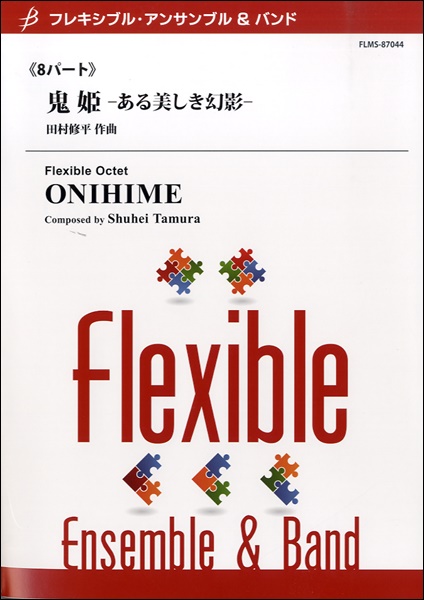
楽曲情報
- 作曲者:田村修平 (Shuhei Tamura)
- 演奏時間:4分40秒(約)
- 編成:フレキシブル8パート
※フレキシブル:様々な楽器の組み合わせで演奏可能な編成のこと
曲について
この作品は、「橋姫伝説」などに登場する“鬼姫”を題材として作曲された木管八重奏曲です。鬼姫としての外面的な印象と、内面に秘められた感情が曲中で対比的に描かれており、構成の明確なコントラストが印象的です。特に中間部の抒情的な旋律は、曲の聴かせどころとなっています。
演奏上は、緩やかな部分と急展開する場面の対比がはっきりしており、それぞれのテンポ感と拍の流れを正確に共有することが求められます。特に3連符が多用されているため、拍感が失われないよう全員の呼吸とリズムをそろえることが重要です。小節の頭が休符となる音形も多いため、無音の中でもテンポを感じ続ける意識を保つ必要があります。
本曲はフレキシブル編成ですが、全8パート中6パートが木管指定のため、実質的に木管八重奏として演奏されることが一般的です。調号は比較的平易で中学生からも取り組みやすい一方、グレードは4と高めで、全国大会での演奏歴もあるように基礎力と表現力の両方を鍛えられる良曲です。冒頭から派手に曲が始まるため演奏効果も高く、聴く印象よりも演奏しやすいため、初〜中級のチームにもおすすめです。
おわりに
今回は木管八重奏のアンコンおすすめ曲をご紹介しました。
近年では木管八重奏もアンコンで良く演奏されておりメジャーな編成となってきました。金管八重奏と異なり、編成の自由度が高いため、編成が合わなかった場合は、今回紹介した曲以外の編成の曲も是非聴いてみてください。
ぜひ、皆さんのチームに合った一曲を選んで、木管八重奏ならではの魅力をアンサンブルコンテストで発揮していただければと思います。
今回の記事が選曲のヒントになれば幸いです。

